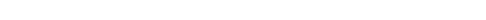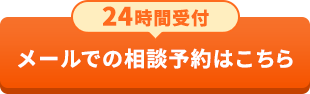遺言書が無効になる場合について
遺言書は、相続財産の帰趨を決め、相続人の方々の将来にも影響を与える重要な書面ですので、作成に法律上のルールがあり、そのルールを遵守していない場合は最悪無効となってしまうことがあります。
せっかく作成した遺言書が無効となってしまうようなことがないように、遺言書が無効になる事由について事前に把握しておきましょう。
この記事では、遺言書が無効になる場合についてご説明します。
自筆証書遺言で無効となるケース
自筆で作成していない場合
自筆証書遺言は、財産目録を除き、遺言者本人が全文を直筆で書くことが必要となります。
そのため、パソコンで作成したり、ボイスレコーダーで録音したりして遺言を作成した場合、その遺言は無効となります。
この要件は厳格で、本文をパソコンで作成し署名欄を自筆で手書きしても無効となります。
また、本人の自筆である必要があるので、他人に代筆してもらうことも無効となる理由となります。(なお、平成30年の法改正で、目録等については自書しないものも活用できることとなりました。)
必要事項が欠けている場合
民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と定めています。
これに沿っておらず必要事項の記載が欠けていたり、不備があったりした場合は、遺言は無効となってしまいます。特に多いのが、遺言書の日付を書き漏れてしまうケースです。
また、書き漏れではなくても日付を十分に特定できないような記載、例えば「○年○月吉日」というような記載も無効となります。日付がはっきり特定できれば「私の〇才の誕生日」という記載も有効とされていますが、年月日をはっきり記載しておくことが無難でしょう。
その他、押印や自署もれにも注意しましょう。自筆証書遺言には、遺言者が、必ず自らの氏名を自書しなければなりません。
なお、署名をするのは、必ず遺言者1名のみであり、例えば夫婦など複数名が同じ遺言書で、共同で遺言をすることはできません。
修正方法が誤っている場合
自筆証書遺言は手書きで作成するので、途中で書き損じて修正したいという場合もあるでしょう。
そうした場合の修正方法は、民法968条2項で「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」と定められており、この様式に沿った修正方法でなければ無効となってしまいます。
具体的には、訂正箇所を二重線等で取消しその上に押印し、その横に正しい文字を記載します。そして、余白箇所に「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で付記し署名をする必要があります。
内容が非常に不明瞭である場合
遺産分割は、遺言書の内容に沿って行われるため、第三者が読んでも明確に意味がわかるような内容にしておく必要があります。
記載の内容が曖昧で色々な意味に読めてしまったり、重要な箇所に誤記があったり、条項同士が矛盾していたりしている場合、いざ遺言書を開封したときに第三者に意図が読み取れないことがあります。
判例では「遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈する」とされており、多少曖昧な箇所があってもそれだけで無効になるわけではありませんが、著しく不明瞭な記述だった場合には無効となる可能性があります。
本人の正常な意思ではないと思われる場合
遺言をするためには、遺言能力といって遺言の内容を理解し、判断する能力を有していることが必要です。
そのため、遺言書の記載や体裁自体は一見有効であったとしても、遺言者が重度の認知症等を患っていたり、病気やケガで意思表示能力を失っていたりする場合、遺言能力がなかったとして遺言書が無効となることがあります。
また、第三者から強要や詐欺にあって遺言をした場合も、その遺言書は無効となります。
公正証書遺言であっても無効になるケース
公正証書遺言は、公証役場において、証人2人の立ち合いのもと公証人という法律のプロが作成するので非常に信頼性の高い遺言方法です。
しかしながら、100%無効とならないというわけではなく、以下のような場合には無効となるケースもあります。
遺言者に遺言能力がなかった場合
上述のように、遺言者に遺言能力がない場合は、遺言は無効です。公正証書遺言は、口授といって、遺言者が遺言書に記載したい内容を口頭で公証人に伝え、それを公証人が書面化するという方法で作成されるため、遺言能力がないということは想像しにくいかもしれません。
しかしながら、実務上は、いきなり当日口授をするわけではなく、事前に公証人と遺言書に書くべき内容についておおむね打ち合わせをし、内容を固めています。当日スムーズな進行をするためです。
したがって、口授当日は、公証人がすでに作成された内容を読み上げ、異存ないかどうか遺言者に最終確認する程度で終わることも少なくありません。
そのため、遺言者が遺言内容を理解できていなくても「はい」と返事をする能力さえあれば、公正証書遺言は作成できてしまうことがあります。
後日、公正証書遺言の存在を知らされた相続人が、作成日当時にはすでに重度の認知症だったので、遺言を理解できるはずがないと考え、遺言無効確認の訴えを起こし、その主張が認められたときには、このような公正証書遺言は無効になってしまいます。
証人が不適格であった場合
公正証書遺言を作成する際には、2名の証人の立ち合いが必要となります。
証人は誰でも構いませんが、例外として、判断能力や公平性の観点から、以下の人は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族
- 遺言を作成する公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員
これらの人が証人となっている場合は、遺言書は無効となります。
最後に
遺言書が無効になる場合についてご参考になれば幸いです。
遺言を作成する場合は、せっかく作ったものが無効になってしまっては意味がありませんので、専門家のアドバイスを受けて有効な遺言書を作成できるようにしましょう。