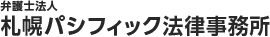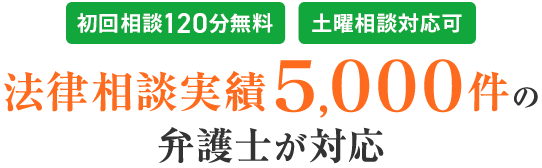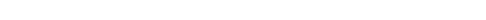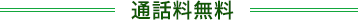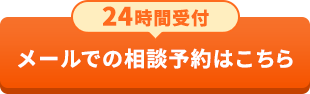遺言書 いきなりのこと 驚いた
| 亡くなられた方 | 母親 |
|---|---|
| 相続人 | 長女(依頼者)・長男 |
| 遺産 | 土地・建物・自動車・預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者の母親が病気になり、医師からは余命宣告を受けておりました。依頼者と弟にあたる長男は、母親の治療方針などをめぐって考え方の違いがあって、徐々に確執が生まれておりました。その中で母親が亡くなり、法定相続人2名の相続手続に移行するはずでした。
ところが、弟は、母親が亡くなる少し前に公証人を病院に連れていき、公正証書遺言を作成していたのでした。その遺言書の内容は、弟に母親のほとんど全部の財産を相続させるというものでした。その内容に不満を持った依頼者は、弁護士への相談へと至りました。
依頼人の主張
依頼者としては、母親の生前の言動から考えて、弟に全財産を遺贈するということをするとは考えにくいところでした。
そのため、前記の遺言書は、母親の真意に基づくものではないということも疑っておりました。
そこで、病院に対する照会やカルテの開示を行い、母親の生前の意思能力等に関する調査を行いました。
ある程度有益な証拠もありましたが、母親に意思能力がなかったことを確実視させるだけのものとまではいい切れないところもあったため、本件では遺言書があることを前提とし、弟に対する遺留分侵害額請求権を行使するという方針で対応することになりました。
サポートの流れ
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内に権利行使しておかなければ、時効によって消滅してしまいます。
そこで、本件ではまず弟に対する配達証明付き内容証明郵便を送って遺留分侵害額請求権を保全しました。
その後に、弟(代理人弁護士)との間で交渉を行って解決を試みましたが、相手方が遺留分を計算するための資料を開示することに応じなかったため、やむなく訴訟を起こして解決を図ることとしました。
結果
訴訟の中では、相手方も遺留分の金額を算定するための不動産や自動車の資料を出さざるを得なかったため、遺産全体を評価するための資料がそろいました。
それを前提とし、裁判所の仲介のもとに訴訟上の和解を成立させ、依頼者の遺留分である遺産の4分の1に相当する金額を確保することができました。
その他の解決事例
| 亡くなられた方 | なし |
|---|---|
| 相続人 | 配偶者・子 |
| 遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
| 亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
|---|---|
| 相続人 | 長女(依頼者) |
| 遺産 | 土地・建物・預貯金 |
| 亡くなられた方 | 夫 |
|---|---|
| 相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
| 遺産 | 不動産・預貯金・証券 |