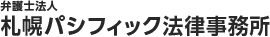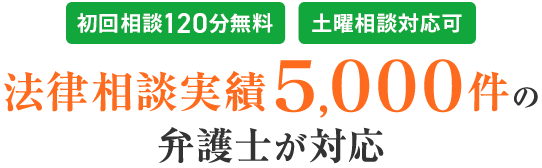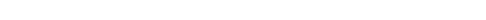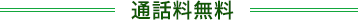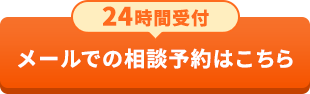縁組で 親族増えた 関係図
| 亡くなられた方 | 姉 |
|---|---|
| 相続人 | 妹(依頼者)・実方兄弟姉妹 |
| 遺産 | 土地・建物・預貯金 |
ご依頼の背景
未婚で子がいない姉が高齢に差し掛かり、近くで唯一の妹(依頼者)がお世話をしていました。
姉は亡くなり、妹に対し自分の財産を残してあげたいという意向があったものの、遺言書を作成しておりませんでした。
戸籍の調査を行ったところ、その姉は幼少時に養子に出されており、実は依頼者が唯一の妹ではなく、養子縁組前の兄弟姉妹が多数人いることが判明しました。
この場合、依頼者だけでなく、養子縁組前の実方の兄弟姉妹も等しく法定相続人に含まれるため、相続権を有していることになります。この状況に困った依頼者は、相談に至りました。
依頼人の主張
亡くなった姉の意向としては、できるだけ世話になった妹に財産を残したいというものだったので、依頼者もその気持ちに従って遺産を取得したいというのが希望でした。
そこで、何とか他の相続人に納得してもらい、財産が細切れになってしまうことを防ぎたいと考えておりました。
また、預金が凍結されて引き出すこともできず、不動産の名義変更に手が付けられないことにも困っておりました。
サポートの流れ
依頼後は、弁護士の職務上の権限に基づき、戸籍をたどっていくことで法定相続人のすべてを調べました。
そして、戸籍の附票などを調査することにより、合わせて関係者の住所を調べました。
関係相続人の住所がわかったあとは、弁護士が状況を伝えるお手紙を作成し、丁重に相続分の譲渡をお願いしました。そうしたところ、大多数の関係者は相続分の譲渡に応じ、一部の関係者は相続分の有償での譲渡に応じてくれました。
その後、それらの関係相続人との間で、「相続分譲渡証明書」を作成し、その相続分が譲渡されたことを明らかにする書類を作成しました。これに基づき、問題なく預金を解約し、不動産の名義変更も実現することができる状況になりました。
結果
関係者の多い相続事件は、取りまとめが大変になる傾向があります。
また、高齢化が進む中で、施設に入っている人、成年後見人が付いている人が出てくることも珍しくありません。
弁護士が間に入ってうまく利害を調整したたため、結果的に円滑な相続を実現することができた事例の一つであるということができます。
その他の解決事例
| 亡くなられた方 | なし |
|---|---|
| 相続人 | 配偶者・子 |
| 遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
| 亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
|---|---|
| 相続人 | 長女(依頼者) |
| 遺産 | 土地・建物・預貯金 |
| 亡くなられた方 | 夫 |
|---|---|
| 相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
| 遺産 | 不動産・預貯金・証券 |